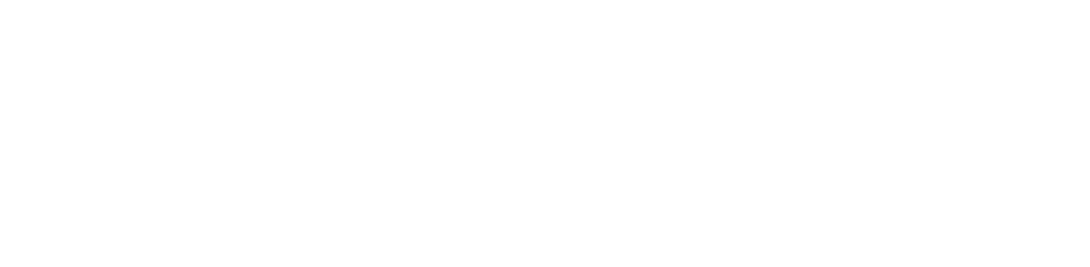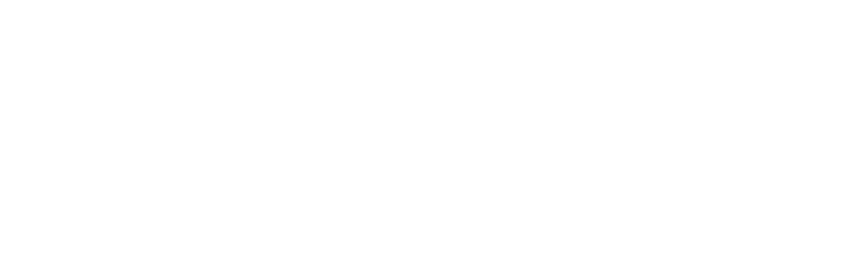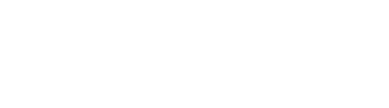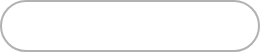学部プロジェクト
統合物語生成システムの
総合的研究
小方 孝
物語生成システムは人工知能や認知科学における挑戦的課題として1970年代から研究開発が行われて来ました。初期には知識表現や推論技術を取り入れた試みが多かったのですが、近年では深層学習など新しい技術を取り入れた研究も現れ始め、また物語論や文学理論と融合した取り組みも増えています。
特に欧米では関連する博士論文も毎年のように現れ(Swartjes, 2010; McIntyre, 2011など)先端的研究領域であり続けていることを示しています。またB.Kybartas & R.Bidarra (2016)は、これまで発表された60以上の物語生成システムを対象に、ストーリーと登場人物など構成要素の生成における自動性の程度を評価する研究を公表しており、この分野の現状での一種の総括となっています。申請者は、既存の多くの研究が特定の理論・技術・方法の検証に傾いているのに対し、自身の試みを多様な技法や知識の統合物語生成システムと位置付けています。
一方国内でも、岡田ら(Okada & Endo,1992)は人工知能のゴール‐プランに基づく物語生成システムを提案、徃住(2007『心の計算理論』)は物語理解・生成に応用可能な多くの研究を紹介しました。最近では研究協力者の深層学習を物語生成に適用する研究も始まっています。さらに近年、芝浦工業大学やはこだて未来大学を中心に物語生成支援システムの商業的利用を狙う取り組みも始まっています。本提案の研究者らはこうした状況の中、小説・映画・広告など多ジャンルの物語を対象にストーリー・言説・修辞などの分析・実験を試みて来ました。
本研究では、統合物語生成システムを対象に、生成される物語の質・その表現の質・生成に使用する知識の獲得効率と質を向上させるために、(A)物語のインパクトを強める修辞機構、(B)物語の見せ方を工夫する表現機構、(C)知識の獲得・学習の賢さを高める知識獲得・学習機構を構築・結合して、統合物語生成システムを拡張します。これにより、物語生成システムの新しい一モデルを提案し、種々の応用的使用や社会的流通実験などへの基盤を構築します。
次の手順で研究を進めます―
(1)次段階を想定して統合物語生成システムの改善を行う
(2)上記(A)(B)(C)を統合物語生成システムとの結合を目的に開発する
(3)この3機構を統合物語生成システムと結合する
(4)物語生成とユーザの受容実験を通じ統合物語生成システムを改善する。
本研究は以上にように総合的な試みであり、平成30年度も以降も継続します。