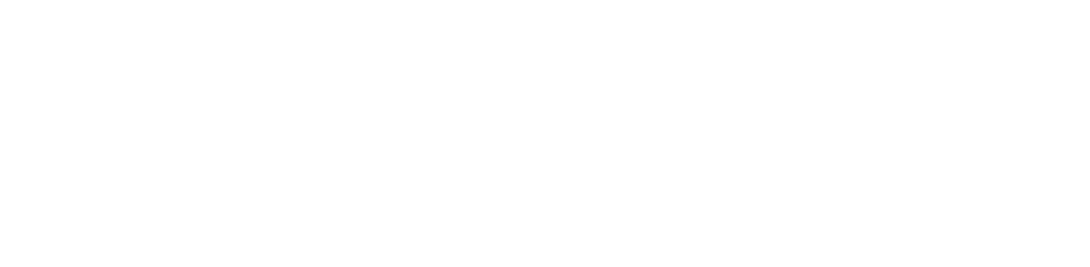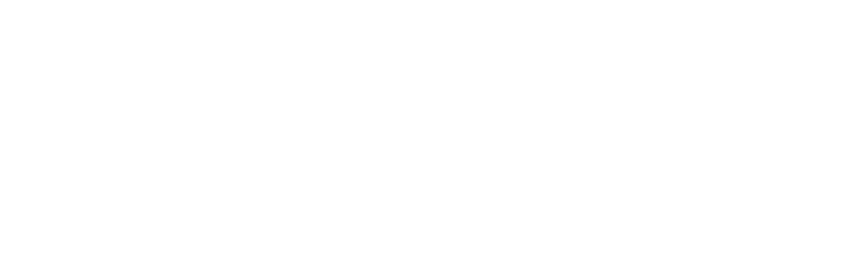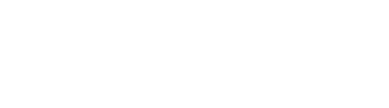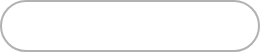大学院進学
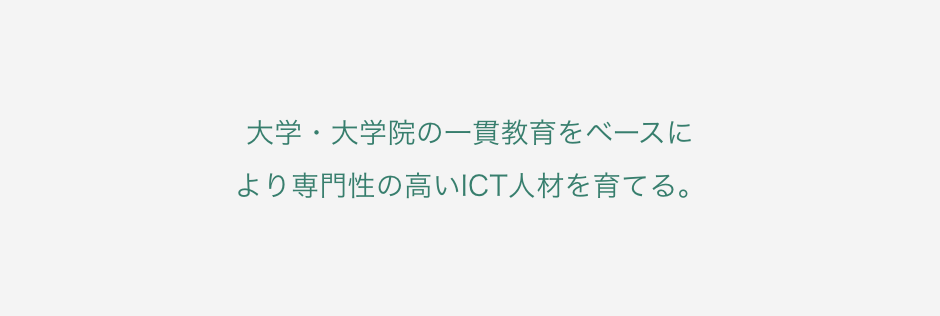
博士前期課程では、学部の4年間を合わせた6年間のスパンで、計画的に高度な専門性を持つ人材の育成のために、学部で優秀な成果を残した学生の推薦入試制度も充実しています。また、博士後期課程では、前期課程よりさらに踏み込んで、より高い研究能力を持った研究者や指導者を養成しています。

少人数教育による実践的研究
少人数教育による実践的研究
1.実践的研究を通じた教育
人や社会のために役立つ研究に主眼をおいた実践的教育を重視。企業との共同研究はもとより、ゼミナールでは課題解決型学習を導入するなど、現場での実践を見据えた教育を行っています。
2.徹底した個別指導・少人数指導
研究を通じて人を育てるという考えに基づき、個別指導・少人数指導を徹底。さらに多様な視点から指導をするため、各学生に1名の主指導教員と2名以上の副指導教員を配置しています。
3.課外講座を通じた教育
長期休暇には、海外の大学と国際交流を行ったり、社会人向けの技術講座に参加する機会を設けています。これらの活動を通じて、広い視野や実践的な専門力を身につけることができます。
4.研究活動の経済的支援
研究活動を支援するために日本学生支援機構奨学金、本学独自の奨学金や授業料免除制度も準備。学会発表を経済的にも支援する仕組みも充実しています。
大学院生メッセージ
大学院生メッセージ
ソフトウェア情報学研究科博士前期課程
紺野 和磨(岩手県立住田高校卒)

もともとパソコンで遊ぶのが好きで、情報系の学部で勉強したいと思って入学しました。ソフトウェアについて少しは理解していると自負していたのですが、実際に授業を受けてみるとわからないことばかり…。でも大学の授業は、理論を学び、演習で実践するという流れで構成されていたので、スムーズに基礎を身につけることができました。
3年次の後期から就職活動が始まったのですが、私も最初は就職希望。しかし、ただ漠然と就職を考えていた自分に疑問がわき、次第にもっと勉強を続けたいという思いが強くなったんです。また、卒業研究も、初歩的な段階でまとめることに中途半端な思いもありました。そんな理由から大学院への進学を選び、学部生の頃から取り組んできた「音声検索」の研究を続けることにしたのです。
大学院では論文を学会で発表する機会が多く、国際会議での発表も経験しました。学会は自分を成長させる場であり、多くの研究者と交流できる貴重な場。研究のスタンスや切り口の新しさなど、刺激を受けることが多く、自分の視野も広がりました。研究を志す学生にとって、大学院は最適な環境が整っていると思います。